深海にまで広がるレアアース争奪戦…米中が太平洋で「水面下の競争」
クック諸島沖の海底にコバルト・ニッケルなど豊富
米国も中国に続き資源開発に参入
日本、米国と連携し南鳥島沖で採掘実験
推定埋蔵量1,600万トン…中国の3分の1規模

米中間のレアアース(希土類)供給網をめぐる競争が、陸地から深海へと拡大している。海底に眠るレアアースは、陸上採掘に比べ環境汚染物質の管理が容易で、埋蔵量も陸地に匹敵するとされるためだ。
太平洋の島国クック諸島は、この海底資源をめぐる米中対立の最前線にある。AFP通信によると、9日(現地時間)、中国の海洋調査船「大洋号」がクック諸島の首都アバルア港に入港し、海底調査を進めているという。
わずか1か月前には、米海洋大気庁(NOAA)の支援を受けた米国籍の調査船「ノーチラス号」も島国クック諸島海域で探査を終えたばかりだ。米中両国の調査活動が相次ぐなか、太平洋一帯は事実上「深海資源の最前線」と化している。
クック諸島の海底には、電気自動車用バッテリーの主要素材であるコバルト、ニッケル、マンガン、そしてレアアースが豊富に埋蔵されている。クック諸島海底鉱物庁は「中国の深海資源局と共同で、海底地形の測量やサンプル採取を実施している」と明らかにした。
クック諸島は今年2月に中国と、8月には米国と深海資源協定を締結し、表面的にはバランスを保っているように見えるが、実際には米中両国の戦略的思惑が交錯する現場となっている。ニューヨーク・タイムズは「中国の調査船は海流や海底地形のデータを体系的に収集しており、将来的に中国が太平洋で潜水艦を配備したり、米国のステルス潜水艦を追跡するために利用する可能性がある」と伝えている。科学協力を名目にした覇権争いの様相を呈しているという。
一方、日本もレアアース確保に本格的に乗り出した。高市早苗総理は6日の参議院本会議で「レアアースの調達経路多様化は日米双方にとって重要だ」と述べ「米国との具体的な協力策を検討していく」と明らかにした。
高市総理は来年1月、南鳥島近海の水深約6,000メートルの海域で、レアアースを含む泥を引き上げる実証実験を予定している。この地域には約1,600万トンのレアアース泥が埋蔵されているとみられ、米国地質調査所(USGS)によると、これは世界最大の埋蔵量を持つ中国(4,400万トン)の約36%に相当する。
高市総理は先月、ドナルド・トランプ米大統領と「重要鉱物・レアアース確保のための枠組み」に署名し、資金支援や備蓄制度、補助金、出資などを含む共同支援体制を整備することで合意した。米国は4月に発令した大統領令で、公海資源の商業化手続きを迅速化し、民間企業の探査活動も認めている。
一方、国際規範を巡って米中の対立は深まっている。国連の下部機関である国際海底機構(ISA)は、公海資源を「人類共通の遺産」と位置づけ、商業採掘の規定を策定中だが、加盟国間の利害対立により合意に至っていない。
その間、中国はISA内での影響力を拡大し、公海探査契約を5件獲得した。理事会や環境委員会にも多くの自国関係者を送り込んでいる。一方、米国は国連海洋法条約(UNCLOS)を批准しておらず、ISAの加盟国ではないため、自国法に基づく独自の許認可制度を運用している。
太平洋島嶼国の立場は分かれている。クック諸島、ナウル、トンガ、キリバスなどは資源開発を通じた経済自立を目指しているが、パラオ、フィジー、バヌアツ、マーシャル諸島などは生態系破壊を理由に商業採掘の中止を要求している。パラオは最近のISA会議で「深海採掘は人類共通の遺産を損なうおそれがある」として、採掘禁止の決議案を提案した。
深海レアアース開発は、陸上採掘に伴う放射性廃棄物や酸性廃水などの環境負担を回避できる代替手段として注目されているものの、堆積物の拡散や海洋生態系の攪乱といった新たな懸念も指摘されている。日本は海水再投入方式で汚染拡散を減らす技術を開発中であり、米国は無人潜水艇を用いて採掘前後の海洋環境をリアルタイムで監視する体制を構築している。
資源業界関係者は「20年前、先進国が環境負荷を理由に陸上採掘から撤退した結果、中国が精錬・加工を独占した。今回は公海資源を巡って『環境か安全保障か』の葛藤が再び浮上している」と語った。





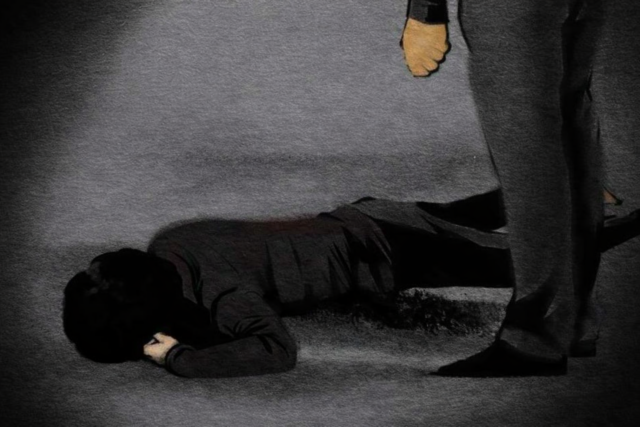
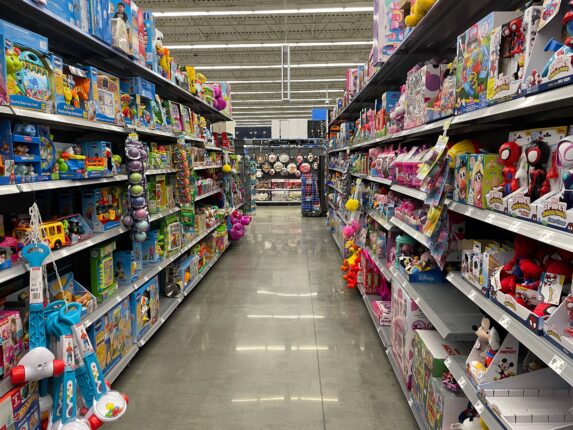



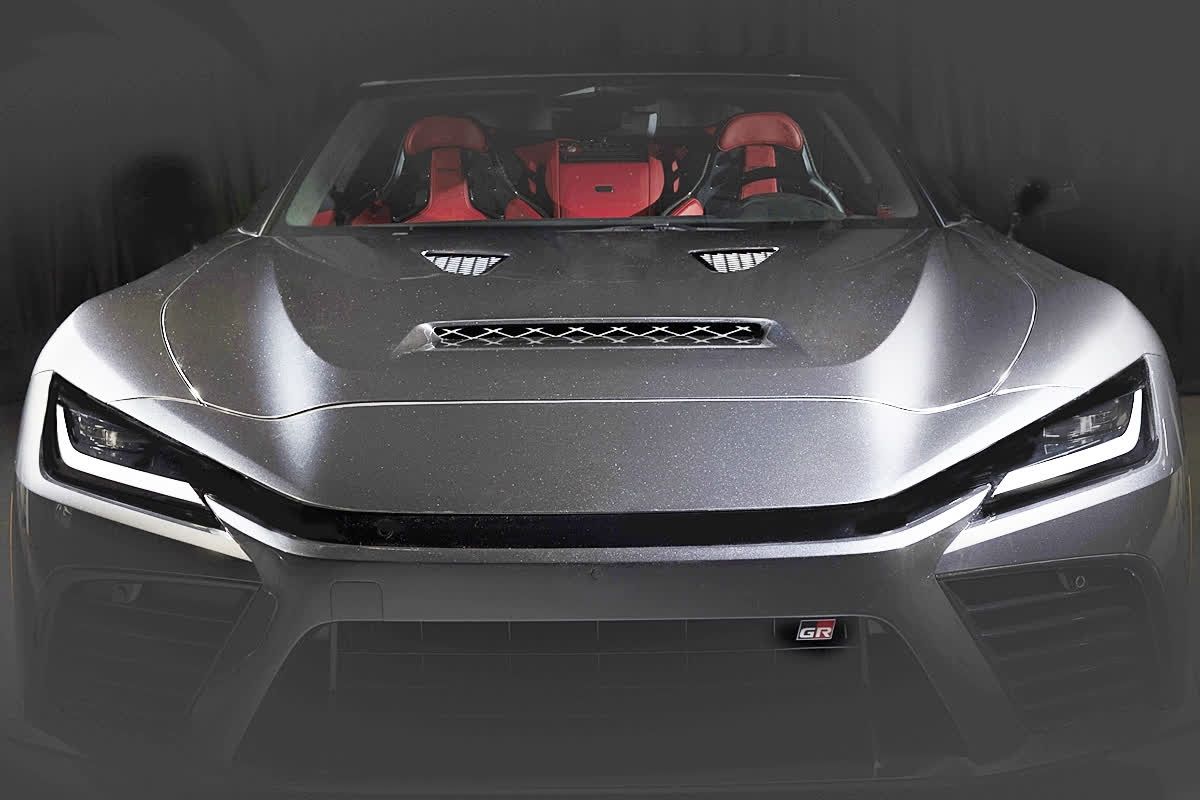











コメント0