A-10の早期退役、有人ヘリの運用中断…戦場の主役はドローンへ
A-10攻撃機は湾岸戦争で、堅牢な機体と圧倒的な火力によって名声を確立し、近接航空支援(CAS)の代名詞とされてきた。攻撃ヘリのAH-64アパッチも、いまなお各国が導入を望む世界最高水準の機体だ。それにもかかわらず、なぜ米軍はこうした戦力を自ら手放そうとしているのか。
答えはドローンにある。ロシア・ウクライナ戦争は、現代戦の主戦力がすでにドローン中心へ移行しつつある現実を浮き彫りにした。ドローンは小型で低コストなうえ、操縦士の生命リスクがない。地上部隊が直接制御できるため、状況に応じた即応打撃が可能となる。
こうした流れの中で、近接航空支援はドローンの役割へと移りつつあり、ヘリコプターによる機動も無人化技術の進歩によって代替が進んでいる。
実際、米軍はブラックホーク・ヘリコプターに無人操縦システム「MATRIX」を搭載し、遠隔操作の試験に成功している。タブレット端末による操作で、兵員や物資の輸送任務も遂行した。完全無人型の「U-ホーク」もすでに公開実験が行われており、操縦士が乗らない軍用ヘリが現実のものになりつつある。

「米陸軍、2〜3年で最低100万機のドローン導入へ」
米陸軍は現在、小型・超小型の物流ドローン導入も加速させている。ヘリコプターでは効率が悪い少量物資の補給を、低コストで迅速に行えるためである。維持費は抑えられ、機動性も高い。
米陸軍長官は最近、「今後2〜3年以内に最低100万機、その後は毎年50万〜数百万機規模でドローンを調達する」と明らかにした。現在の年間約5万機から一気に拡大する計画で、ウクライナとの大規模なドローン協力も進めている。
保守的とされる軍組織が急速に変化している背景には、戦場でドローンが既存兵器を圧倒する光景を繰り返し目にしてきた現実がある。ドローンを備えた部隊は、そうでない部隊を一方的に制圧できるとされる。
米軍が進める「ドローン中心の軍事改革」は、兵器史における大きな転換点として記録される可能性が高い。米軍は情報・指揮系統でウクライナ軍と連携する過程で、ドローンが戦争の形をどう変えているのかを詳細に観察してきた。現在の変化は、その実戦分析に基づいたものである。

ドローンは「資産」から「消耗品」へ
これまでドローンは最先端兵器であると同時に、高価で取り扱いの難しい「資産」と位置づけられてきた。そのため開発や調達は国防省や各軍の最高指揮部が管理し、現場部隊は支給されたドローンを慎重に運用する必要があった。
しかし、ピート・ヘグセス国防長官が7月に発表した新たなドローン政策で、その考え方は一変した。前線部隊の指揮官が上層部の承認なしに、市販品や3Dプリンター製ドローンを自ら調達できるようになった。さらに小型ドローンは「資産」ではなく「消耗品」と位置づけられ、損失を前提に自由に使用する方針に転換された。
今後はすべての戦闘員がドローン運用教育を受け、AI基盤のデータベースを通じて技術やノウハウを共有する体制が構築される。
この方針転換により、前線部隊では独自のドローン開発が加速している。米陸軍第10山岳師団は、市販ドローンにAI自律飛行ソフトと迫撃砲弾搭載装置を組み合わせた攻撃用機体を開発した。第173空挺旅団戦闘団は、小型FPVドローンに指向性対人地雷クレイモアを搭載し、敵ドローンの迎撃に成功している。さらに第1海兵師団は、商用ドローンを改造し、最大220kgの弾薬と食料を運べる物流ドローンを試験運用中である。
地位や階級を問わず現場から新しい発想が次々と生まれていることが、米軍で自由発想型のドローンが次々と誕生している背景である。












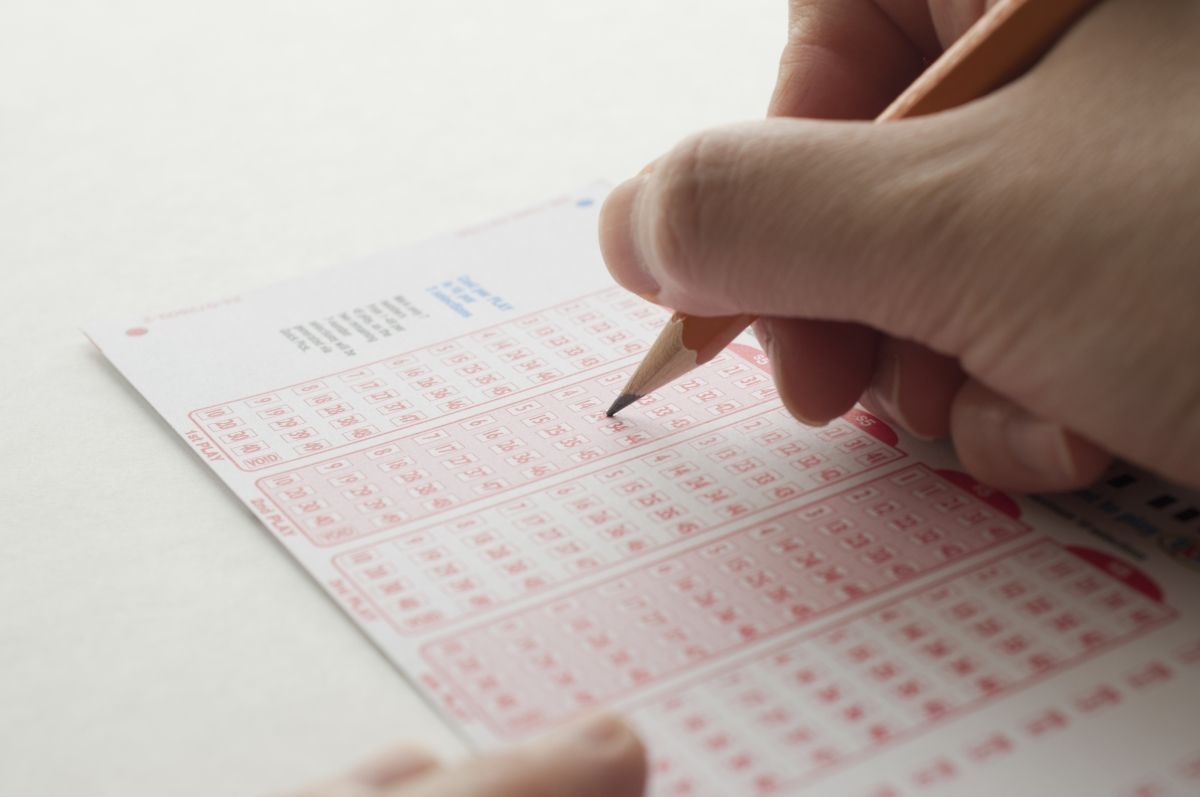









コメント0