
欧米で敬遠されてきた内臓肉が、近年では環境・健康の観点から「持続可能なタンパク源」として再注目されている。栄養学的価値、フードロス削減効果が同時に確認され、欧米でも内臓消費拡大を主張する声が力を得ているとの分析だ。
『インディペンデント』は3日、欧米諸国でも内臓肉の摂取を増やすべきだとの議論が広がっていると報じた。『ノーズ・トゥ・テール』(Nose-to-Tail)哲学を再導入し、食肉処理された動物のすべての部位を活用しようとする概念である。欧米圏ではこれまで筋肉(ステーキ・ラムレッグなど)中心の消費が絶対的で、心臓・肝臓・腎臓など内臓部位は低価格の肉とみなされ、多くが輸出されるのが一般的だった。
しかし内臓肉は栄養学的にはむしろ「高栄養食品」とされる。肝臓100gには1日推奨鉄分の36%が含まれ、挽き肉の約3倍にあたる。ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸も豊富だ。
研究チームが英国の肉食消費者390人を調査した結果、健康を優先する消費者ほど内臓料理をより美味しく感じるだろうと予想する傾向が見られた。ただし内臓そのものを『汚れていそう』、『気持ち悪い』と思う社会的スティグマと文化的拒否感は依然として大きな障壁となっている。
内臓摂取拡大は環境的意義も大きい。同じ量のタンパク質を得るために食肉処理すべき動物の数を減らし、フードロスと畜産由来の温室効果ガス排出を削減できるからだ。このため一部のサステナビリティ研究者は「内臓消費は最も現実的で倫理的な肉食転換だ」と評価している。
そもそも内臓活用は人類が狩猟採集していた時代から続く最も古い方法である。動物を一頭捕らえたら廃棄する部位なく全てを食べるという生存技術から始まり、古代国家・宗教儀式の供物文化へとつながった。韓国の『コプチャン』、フランスの『アンドゥイユ』、ペルーの揚げ胃料理『モチンチータ』など世界各国の内臓料理は、この生存文化の調理技術の多様性が生み出した結果である。
近年の高物価時代に入り、内臓は欧米でも「安い肉」ではなく「持続可能な肉」と再解釈されている。ミシュランシェフの中にはすでに内臓メニューを再び導入し始めており、英国の若手シェフの間でも伝統的な『オフル』メニューの現代的解釈が増えている。
内臓は嫌悪や貧困の象徴ではなく、人類が最も長く検証してきたタンパク質消費方式であり、環境・栄養・文化が重なる文明型食材だという認識転換が始まったものとみられる。






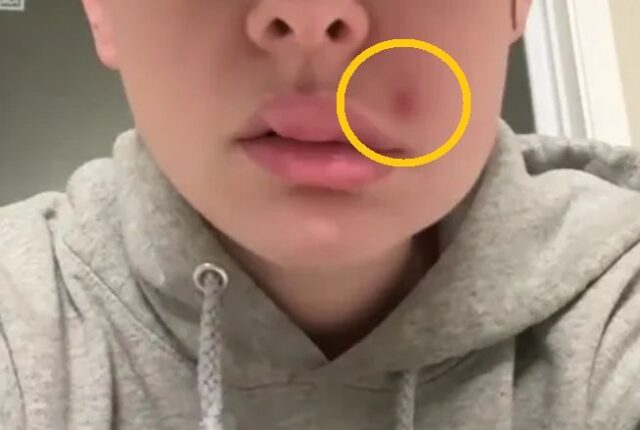





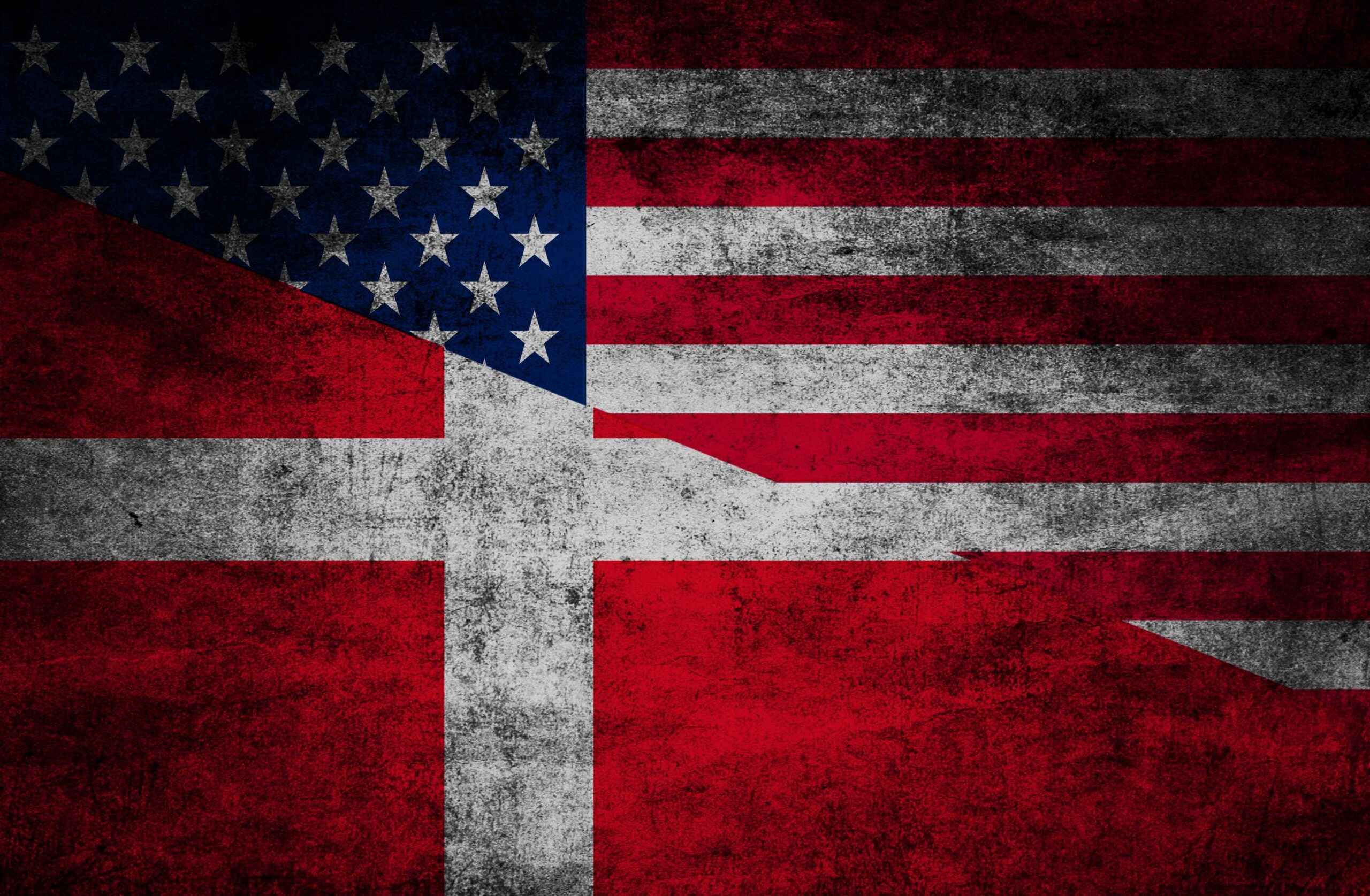








コメント0