
中国の習近平国家主席が主導する官庁の「綱紀粛正運動」により、中国の内需経済が凍結状態に陥っているとの分析が出ている。中央の指示が地方に伝わるにつれ、より厳格かつ硬直的に適用されるため、中国の国営メディアまでもが「規定を誤解しないように」と呼びかける事態になっている。しかし、一度始まった様子見の姿勢はさらに強まる見通しだ。
9日の中国メディアの報道によると、中国政府は公務員の浪費防止政策に対する誤解を払拭するため積極的に動いているという。中国国営の新華社は最近の論評で「一部の地域の公務員が(浪費防止政策に対する)過剰な解釈により、24時間禁酒、食事人数3名制限、食費の各自負担義務化などを実施している」とし、「これは政策に対する誤解と民生への無関心の結果だ」と指摘した。
共産党の公式見解を代弁する新華社のこの論評は、過度な引き締めがかえって民生を軽視する行為だと定義したものだ。新華社だけでなく、人民日報も「緊縮政策は浪費的で贅沢な行為を精密に抑制する『メス』のように使用されるべきだ」とし、「一部の地域がこれを『ハンマー』のように振り回しているのは大きな問題だ」と直接的に批判した。
中国のメディアが言及した浪費防止政策とは、3月から中国共産党が本格的に展開している「中央八項規定の精神を深く貫徹するための学習教育を全党での展開に関する通知」と呼ばれる綱紀粛正運動を指す。八項規定は党政幹部の特権意識や贅沢な風潮、官僚主義を打破する内容で、習主席が2013年に政権を握った際に制定したものだ。これが今年に入って再び強調されている。
習主席はなぜ今年再び綱紀粛正を推進したのか。専門家たちは、3期目の任期中の習主席にとって、4期目に向けて今年が極めて重要な年であることを理由に挙げている。2027年の4期目実現のためには、今年の4中全会(中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議)を皮切りに本格的な青写真を描く必要があるからだ。強力な統制で官庁をまず掌握しようという意図が反映されているとの見方だ。
中国共産党は党総書記(習近平)の5年任期中に毎年1回以上全体会議(中全会)を開催するが、各会議の性格は少しずつ異なる。2022年の1中全会では、発足したばかりの習近平政権3期目の指導部構成が完了した。2023年の2中全会では国家機構の再編案が確定した。2024年の3中全会では経済を中心に核心課題が議論された。
近く開催される可能性がある4中全会は最も政治色の強い会議だ。次期指導体制の骨格が4中全会で決定される。すでに党と軍を完全に掌握している上に、4期目を望む習主席が権力の長期化に対する懸念を払拭するため、一人ではなく集団指導体制を示唆したり、暗に後継者と解釈される可能性のある人物を前面に押し出すジェスチャーを取ったりする可能性もある。
米国の一部保守メディアや反中国家を中心に、いわゆる「習近平失脚説」が広がっているのもこうした理由からだ。揺さぶりをかけるなら今しかなく、習主席が本心はどうあれ、長期的に統治構造を調整するように見える案を提示する可能性があるからだ。習主席は2019年の19期4中全会でも「国家統治体系と能力の現代化」を提案しており、これは指導体制の再編として解釈されたが、結果的には長期政権の布石だった。
政治的転換点を前に引き締めを図ったところ、現場への影響は甚大だ。浪費・腐敗を減らせと言われると、ただ全てを削減してしまう。北京などで活動するロビイストは中国の現地メディアとのインタビューで「ほとんどの地域で公務員がどの支出が許可され、どの支出が禁止されるのかを明確に知る指針がない」とし、「あらゆる食事支出を断っているが、(地域経済には)非常に破壊的な影響を与えている」と述べた。
実際、中国メディアの報道によれば、一部の地方政府は公務員や公共機関の職員を対象に毎日飲酒検査を実施したという。つまり、酒を一切飲んではいけないということだ。公務員が夕食を外食する姿を通報すれば、報奨金を与える制度を導入した自治体もある。広東省の民間シンクタンクの代表も「政府の緊縮キャンペーンは特に3~4線級(中小規模)都市に大きな影響を与えている」とし、「こうした都市は産業基盤が弱く、公共部門の消費が地域内需の中核を占める場合が多い」と指摘した。
匿名を条件に現地メディアとインタビューしたある経済学者は「公務員は本当に恐怖に怯えており、一緒に会ってコーヒーさえ飲めない状況だ」とし、「中央政府は通常の外食や飲酒を禁止していないが、どの食事が通常の外食なのかを判断するのが難しい状況で、下位政府機関が独自で追加規制を導入している」と述べた。
公共部門のロビー活動の象徴的存在である高級白酒「茅台」と「五糧液」の株価が13~14%下落したのもこれと無関係ではない。官庁の雰囲気は民間にも波及している。北京の一部の法律事務所は政府と同様の外食及び飲酒制限を従業員に適用し始めた。もともと内需不振に苦しんでいた中国にとっては、深刻な打撃となることは避けられない。
「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」は6月の報告書で、中国の外食産業の売上の約51.6%が政府機関と国営企業、公共機関の消費によるものだと分析した。EIUは「この部門の支出が10%減少すれば、外食産業全体の売上は5.2%ポイント下落し、中国全体の小売販売は0.6%ポイント低下する」と診断した。また「経済成長率自体への影響は微小に見えるかもしれないが、雇用面では非常に大きな波紋を呼ぶだろう」と付け加えた。
日系投資銀行の野村證券も同様の分析を発表した。野村證券は「今回の緊縮と旧製品買い替え支援政策の鈍化などを考慮すると、今年上半期に5.0%を記録した中国の小売販売増加率は下半期に3.1%まで落ち込む可能性がある」と予測した。
それでも地域政府が中央指導部への忠誠心を誇示するために、より厳しい規制を導入する悪循環は続く見込みだ。内需消費拡大の目標自体を損なう事態に至る可能性があるとの分析が出ている。広州大学で研究するある教授は「最近、広州の地域官僚が過度の飲酒で死亡した事例や豪華宴会に関する報道がメディアに取り上げられるなど、規則強化の引き金になる出来事が相次いでいる」と述べた。




















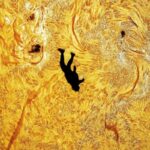

コメント0