
米国よりも早くステーブルコインを法制化した日本だが、市場の活性化には苦戦している。いわゆる「規制の先取り」と「市場の革新」との間でバランスを見出せなかった結果として、法的地位を認められた日本円連動型ステーブルコインは現在のところ存在していないという。
このため、ウォン連動型ステーブルコインの議論が活発化している韓国でも、日本の事例を教訓とすべきだという声が上がっている。
23日、仮想資産業界によると、日本円連動型ステーブルコインを手がけるJPYC株式会社は今月初め、日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)に資金移動業分野の「第2種会員」として加入したという。資金移動業分野でJVCEAに第2種会員として登録されたのは、今回が初めてとのこと。
JPYCが第2種会員を取得したのは、「初の公式な円連動ステーブルコイン」の発行を目指す狙いがあるという。国内では2023年6月から、ステーブルコインを現金と同等の電子決済手段として認める内容の資金決済法改正が施行されている。世界の主要国に先駆けてステーブルコインを制度化した。
しかし、発行主体が銀行や資金移動業者、信託会社などに限られ、中継事業者にも「電子決済手段取引業」への登録義務が課されるなど、厳しい発行条件が障壁となっている。このため、法的に認められた円連動ステーブルコインは今のところ確認されていないとのこと。
JPYCも2021年から日本で初めて円連動型仮想資産「JPYC」を発行しているが、資金決済法上はステーブルコインではなく「前払式支払手段」として分類されていた。これは、JPYCが法律上の資金移動業者ではなかったためだという。
同社では、JPYCを公式なステーブルコインとするため、法的地位の確立に向けた手続きを進めている。まずはJVCEAの第2種会員資格を得たことで、今後は金融庁に対して資金移動業者としての登録を申請する方針を明らかにしている。JPYCが法的地位を確立すれば、実際の決済や円との交換にも制限なく対応できるようになる見通しとのこと。発行時点での流通規模については100億円程度と試算されている。
日本ではJPYC以外にも複数のステーブルコインが存在しているものの、実用化にには至っていないという。石川県の地方銀行である北國銀行が発行する「トチカ」は、実際に決済手段として利用可能だが、使用できるのは石川県内に限られている。
インターネット・金融大手のGMOが発行する「GYEN」も、国内の制度内において信託会社を通じて発行されていないため、国内での流通や居住者への配布は認められていない。
こうした中、仮想資産業界の一部からは、日本の事例を教訓とすべきだとする主張も出ており、ステーブルコインを既存の制度にそのまま当てはめようとするアプローチには限界があると指摘されている。
DSRV未来金融研究所のソ・ビョンユン所長は、「日本や欧州連合(EU)のように、既存の銀行中心の枠組みに無理やり当てはめる法制度では、活性化は難しい」とし、「韓国はシンガポールや香港のように、規制とイノベーションのバランスをうまく取る必要がある」と述べたという。












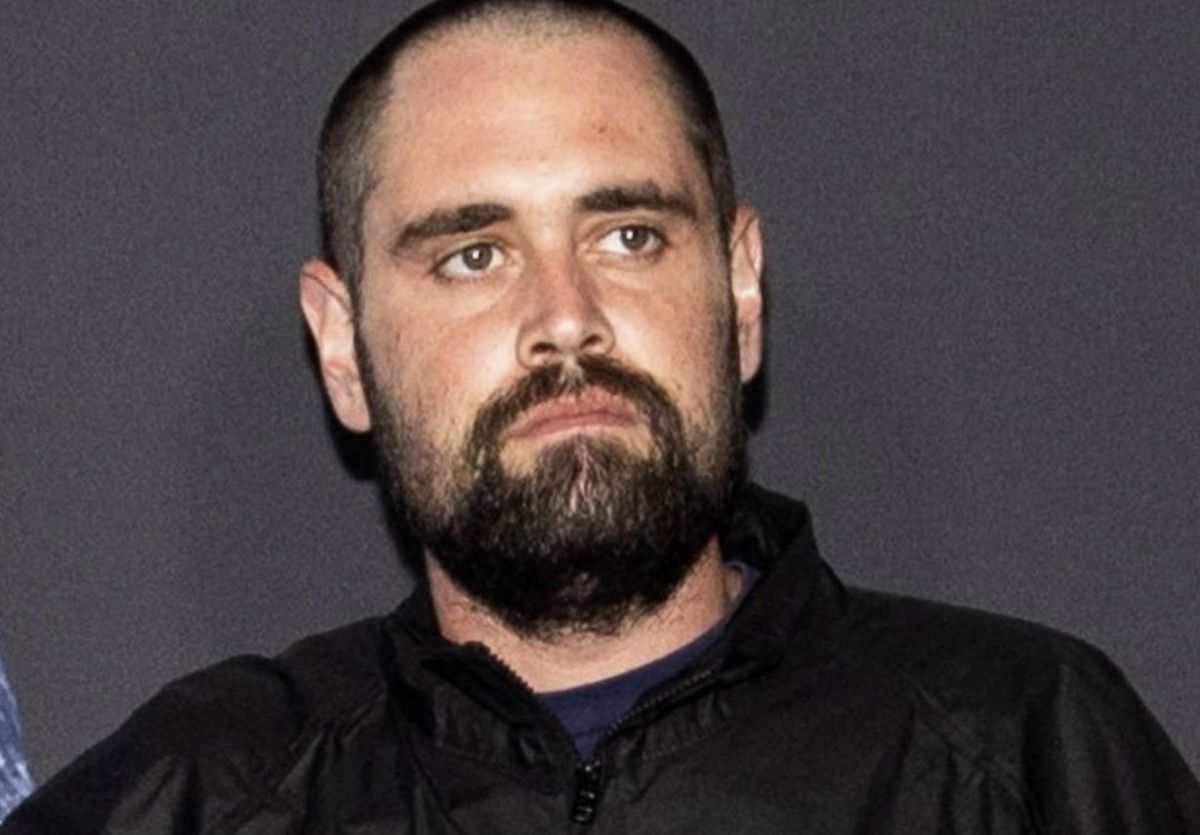





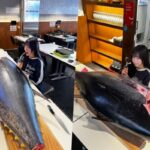



コメント0