
26日の午前9時、鹿児島県・種子島宇宙センターで次世代「H3ロケット7号機」が火を噴きながら空へ飛び立った。国際宇宙ステーション(ISS)に物資を送る日本の新型無人補給船「HTV-X1」を搭載していた。ロケットは発射14分後に軌道投入に成功した。商業用打ち上げ市場参入を狙う日本の主力H3は、これで5回連続成功を記録した。単なる輸送を超え、冷蔵サンプル保管と自家発電が可能なHTV-X1も初飛行で宇宙進入に成功した。
国内のメディアは「H3がついに実用段階に入った」とし、今回の打ち上げを日本の宇宙産業が信頼を回復した転換点と評価した。また、HTV-X1の商業利用拡大への期待も高まった。初期の失敗と打ち上げ遅延で遅れをとっていたとされる日本が、今回の成功を機にようやく安定軌道に乗ったとの見方もある。日本の宇宙産業は今、どこまで来ているのか。
宇宙は米中間の覇権争いの新たな戦場になって久しい。米国は2019年に「宇宙軍」を創設し、宇宙空間を「第5の戦場」と位置づけ、中国は2021年に独自の宇宙ステーション「天宮」を完成させ、宇宙を国家間競争の主戦場にしている。日本もこの隙間で同盟国である米国に協力しつつ、独自の「第3の道」を模索している。
特に「安全保障と産業の融合」という高市早苗内閣の経済安保構想は、宇宙政策強化へと展開している。日本の宇宙スタートアップ業界は、高市内閣の発足以降、一層活気づいている。高市総理は、経済安保担当相時代から科学技術と宇宙政策に直接関与し、「宇宙安全保障構想」と「核融合戦略」を主導してきた人物である。
高市総理は著書で「スペースデブリ(宇宙ごみ)を除去するアストロスケール、小型衛星を製造するシンスペクティブ、衛星画像を活用するアクセルスペースなど、これらの宇宙企業の技術が日本の宇宙産業の潜在力を象徴している」と紹介した。彼女が4日に総裁選で勝利すると、実際にこれら企業の株価が一斉に急騰した。
月着陸船技術を開発するアイスペースの野崎順平CFOは「経済安保を重視する総理の登場が業界には大きな追い風」と歓迎した。

日本は2008年に「宇宙基本法」を制定し、宇宙を科学ではなく、産業・安全保障の領域に引き上げた。続いて2023年から施行中の「宇宙基本計画(2023~2028)」を通じ、政府・自治体・民間が共に参加する体制を構築した。その後、三菱重工業はH3打ち上げ事業を引き継ぎ、国際受注競争に乗り出し、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は民間企業との協力拡大を公式化した。
政府が掲げた宇宙産業目標は具体的だ。2030年代までに民間を含む年間30回のロケット打ち上げ、他国の位置情報システム(GPS)に依存しない独自衛星航法システムの段階的な構築、2029年まで「線状降水帯」予報精度の向上、2020年代後半に日本人宇宙飛行士の初月面着陸実現がそれに当たる。宇宙産業市場規模は2020年の4兆円から、2030年代初頭には8兆円へ倍増を目指す。このため、日本は2023年から2033年にかけて1兆円規模の「宇宙戦略基金」を順次投入している。
この拡張戦略の中心には、同盟国である米国との協力がある。日本は、米航空宇宙局(NASA)が主導する「アルテミス計画」に主要パートナーとして参加し、月周回有人拠点「ゲートウェイ」のモジュール設計と生命維持システムの提供を担当している。有人探査車の共同開発にも参加し、2020年代後半には日本人宇宙飛行士の月面着陸も目指す。宇宙は、日米両国が技術と安全保障を共有する新たな協力の舞台になっている。
民間部門でも動きが加速している。アストロスケールは英国・米国政府と協力し、デブリ除去技術を商業化、インターステラテクノロジズはトヨタ系列から7億円の投資を受け、小型ロケット開発に乗り出した。アクセルスペースは地球観測データを販売して事業領域を拡大し、シンスペクティブは合成開口レーダー(SAR)衛星を活用し約1億ドル(約152億854万円)の資金を調達した。アイスペースはNASAと共に月資源採掘プロジェクトを進行中である。
ただし、まだ越えるべき壁は多い。世界の衛星打ち上げ市場の60%をSpaceXが占め、資本力・スピード・市場開放性のすべてにおいて日本は依然として後れを取っている。日本は技術の信頼性と打ち上げの安定性を武器に「安定型打ち上げサービス」という独自路線を構築する戦略を立てているが、この戦略が実際に通用するかはまだ未知数である。
韓国も昨年、韓国宇宙航空庁(KASA)設立を機に独自の宇宙産業体系構築に乗り出した。両国とも、宇宙を科学技術を超えた経済安全保障の核になる産業と認識している点で方向性は似ている。しかし、日本が政策・産業・民間を有機的に結びつけ、一貫した戦略を加速させるのに対し、韓国は宇宙庁のリーダーシップ欠如と不確実性の中で推進力が弱まっているとの指摘がある。ある業界の関係者は「政策の速度と方向性を安定的に確保できなければ、急変するグローバル宇宙競争で後れを取る可能性がある」と述べた。













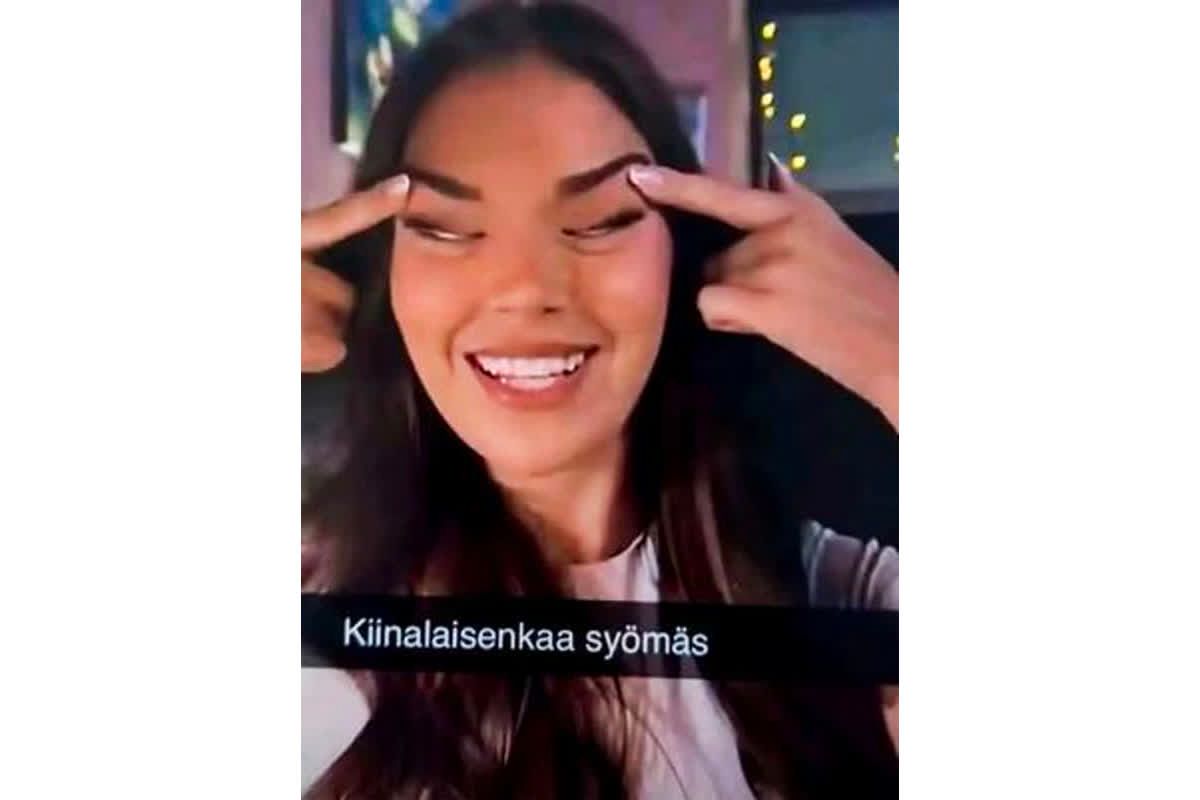








コメント0