
人間は幼児期に急速に成長し、再び思春期になると身長と体重が急激に伸びる「成長スパート」現象が見られる。これにより成人に近い身体発達が達成される。宇宙の天体も似たような過程を経ることが知られている。
こうした中、イタリア、英国、米国、ドイツ、ポルトガル、アイルランドの6か国共同研究チームは、地球から約620光年離れた場所で約60億トンの宇宙ガスと塵を吸収し、異常な成長スパートを遂げている若い漂流惑星を発見したと8日に発表した。
この研究にはイタリア国立天体物理学研究所(INAF)のパレルモ天文台、ボローニャ大学の物理・天文学科、英国セント・アンドリューズ大学の物理・天文学部、ロンドン大学(UCL)の宇宙科学研究室、米国ジョンズ・ホプキンズ大学の物理・天文学科、欧州南天天文台(ESO)、ポルトガルリスボン大学の天体物理学・宇宙科学研究所、アイルランド・ダブリン高等研究所の宇宙物理学部、ダブリン大学(UCD)物理学科の研究者が参加した。
この研究結果は天文学と物理学分野の国際学術誌「アストロフィジカルジャーナル・レターズ』(The Astrophysical Journal Letters, ApJL)」の10月2日号に掲載された。「星間惑星」とも呼ばれる「浮遊惑星(Rogue planet)」は、惑星と同程度の質量を持つが、恒星や褐色矮星の重力に束縛されず宇宙空間を独立して移動する天体だ。宇宙空間を独立して移動するともいうが、銀河中心を単独で公転しているとする研究もある。
研究チームはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)とチリのアタカマ砂漠にあるESOの超大型望遠鏡(VLT)を用いて、誕生したばかりの浮遊惑星がどれほど急速に物質を降着しているかを観測した。降着とは、天体物理学において重力的または静電気的な作用により、宇宙円盤中の物質が特定の天体に螺旋状に落下して集積される現象を指す。実際、恒星や惑星は降着過程を通じて成長する。
研究チームは、南半球でのみ観測される小さな星座に位置し、地球から約400~700光年離れているカメレオン座の浮遊惑星「Cha 1107−7626」を調査した。Cha 1107−7626は地球から約620光年離れた新生惑星で、木星の5~10倍の質量を持つとされる。8月の観測時には、惑星の成長速度が1秒当たり60億tに急上昇し、これは数か月前と比べて約8倍増加した数値だった。研究チームによれば、Cha 1107−7626の成長スパートは、これまで観察された惑星の降着現象の中で最も強力だったという。
また、若い恒星と同様に、惑星の磁場が物質を引き寄せる上で重要な役割を果たすことも今回発見された。JWSTの観測データによれば、惑星の化学組成も成長過程で変化したことが示されたという。惑星形成直後には観測されなかった水蒸気が、成長スパート期には検出された。今回の観測は、磁気活動を通じて膨大な物質が惑星に流入し得ることを示し、惑星も恒星に似た形で成長できることを明らかにしたと研究チームは説明した。
研究を主導したジョンズ・ホプキンズ大学物理・天文学科のレイ・ジャヤワルダナ科長は「今回の観測結果は、恒星の周りを公転しない浮遊惑星が初期段階でどのように振る舞い、成長するかを理解する手がかりを与えてくれる」とし、「浮遊惑星の形成初期は我々が認識していたよりもはるかにダイナミックに見える」と述べた。















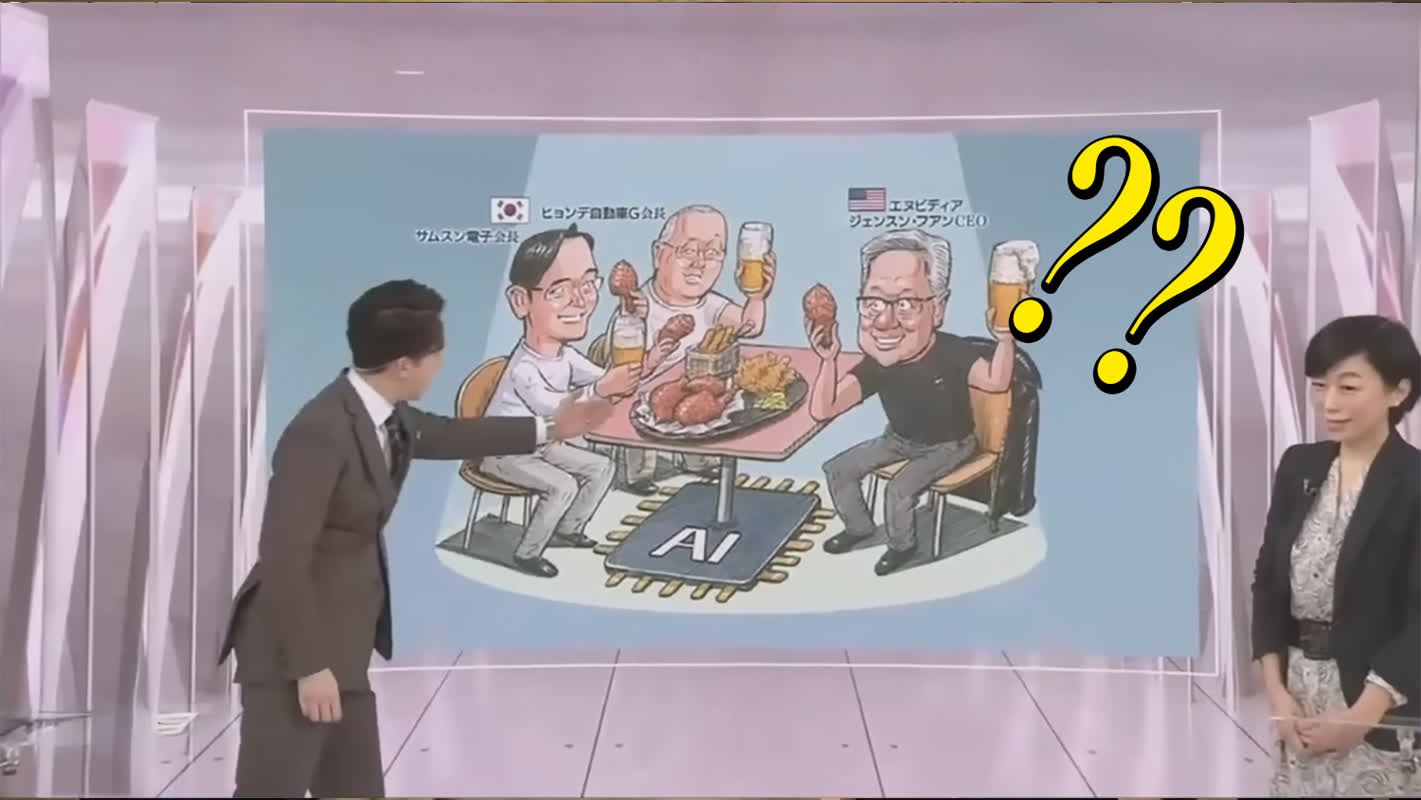






コメント0