近年、寝室のインテリアトレンドに合わせて間接照明や豆電球をつけて眠る人が増えている。
心地よい照明は心を落ち着かせ、空間に温かみを加える。特に、就寝前に柔らかな光の下で読書や音楽鑑賞をする習慣は、日々の疲れを一時的に忘れさせる効果があるとされる。しかし、このような微弱な光が睡眠の質や健康に与える影響は、想像以上に複雑な問題だ。
間接照明には通常、低輝度で暖色系(オレンジ系)のLED照明が多く使用される。このような照明は、白色光や蛍光灯よりも目への刺激が少ないため、心理的な安定感をもたらすという研究結果もある。しかし、どんなに微弱な光であっても、睡眠中に継続的な影響を与えるようであれば体内リズムを乱す可能性があるため、注意が必要だ。

人間の睡眠は「メラトニン」というホルモンと密接に関連している。このホルモンは暗い環境で分泌が活発になり、自然と眠気を誘うことで熟睡を促す。逆に、明るい照明の下ではメラトニンの分泌が抑制され、入眠しにくくなり、浅い眠りに留まる可能性が高くなる。特に、スマートフォンやテレビ画面などのブルーライトに長くさらされている場合、その影響はさらに顕著になる。
間接照明のように明るさと色の温度を調整できる照明であれば、比較的影響が少ない可能性がある。特に赤系の照明は、メラトニンの分泌をあまり阻害しないと言われており、眠る際につける電気として適しているとの評価もある。しかし、完全に消灯して寝る習慣のある人々に比べると、間接照明をつけたまま寝る人々の睡眠の質の方が低いという研究結果も存在する。
例えば、米国のノースウェスタン大学の研究によると、実験参加者が暗い部屋で眠る場合と比べ、わずかに照明のある部屋で眠った後の方が血糖値と心拍数が高くなったという。これは、睡眠中も体が完全にリラックスせず、一種の警戒状態を維持していたことを示唆している。また、夜間照明が睡眠の深さに影響を与え、脳の回復機能が低下する可能性があるとの指摘もある。
このように、光は単なるインテリア要素を超え、睡眠の質と全体的な健康に影響を与える重要な環境要因である。だからといって、間接照明の使用を全面的に否定する必要はない。間接照明を健康的に使用する方法は十分に存在する。

まず、就寝前の読書や瞑想などで照明が必要な場合、色の温度が低く眩しさのない製品を選ぶことが望ましい。就寝直前まで照明をつけておくのではなく、寝る15~30分前から徐々に照明を落としていき、体と脳を睡眠状態にさせる準備をするルーティンが効果的だ。また、照明はベッドのすぐ横や目の位置より下に設置し、直接光が顔に当たらないよう配置することが望ましい。
完全な暗闇だと不安を感じやすい人や子どもは、暗闇で眠るのが難しく、豆電球を使用することも多い。この場合、最小限の明るさに調整可能な製品を使用するか、一定時間が過ぎると自動的に消灯するタイマー機能付きの間接照明を活用すると良い。脳が深い睡眠段階に入る時間帯に光が遮断されるよう誘導する方法だ。
最後に、寝室の環境を全体的に点検することも重要だ。カーテンが薄すぎて外部の光が漏れてこないか、照明の明るさが必要以上に強くないか、電子機器等から発せられるわずかな光が睡眠を妨げてはいないかなどを確認する必要がある。
まとめると間接照明は、心理的安定感とインテリアの満足度の面で良い役割を果たすことができる。しかし、光が人体の体内時計に与える影響を考慮せずに使用してしまうと、健康に不必要な負担をかける可能性がある。
良質な睡眠を望む人々は、目に見えない環境要因にもより注意を払うべきだ。間接照明は「寝る前までの道具」として使い、就寝後は消すことが健康的だといえる。













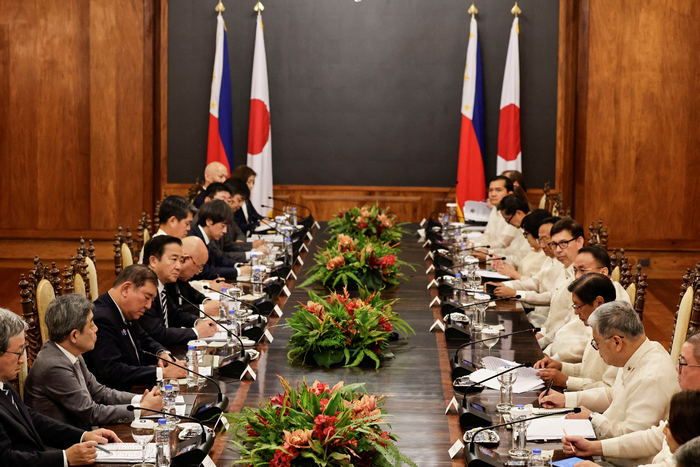








コメント0