
業績不振に陥った日産自動車が、構造改革の規模を当初計画の2倍以上に拡大し、2万人に及ぶ人員削減を行うことになった。
12日、NHKは、日産が当初発表した9,000人を1万1,000人上回る2万人の従業員を削減すると報じた。これは全従業員の約15%に相当し、国内外の事業所で構造改革が実施される見込みだ。
日産は先月、株主に対し2025年3月期の構造改革費用として最大7,500億円の純損失を予想していると明らかにした。同社は米国と中国市場での競争激化により、収益見通しを継続的に下方修正してきた。9日には九州福岡県北九州市に建設予定だった電気自動車用バッテリー工場の計画を撤回した。
低迷する事業の立て直しを図り、日産は昨年12月にホンダとの持株会社設立で合意したが、両社の力関係の不均衡により交渉が決裂。その後、日産の経営状況は26年ぶりの最悪の事態に陥った。
朝日新聞は日産の業績不振について「主力市場の米国ではブランド価値が低下し、新型車の投入が滞っている。中国でも電気自動車競争などに押され、販売台数が減少している」と分析した。
日本経済新聞も「インドとアルゼンチンでの生産撤退などコスト削減を進めてきたが、販売実績と生産能力の乖離が大きく、再建には大幅な人員削減が不可欠と判断した」と指摘した。
日産は営業キャッシュフローの悪化に加え、大規模な負債の返済期限も迫っている。ブルームバーグ通信によると、日産と関連会社は今年16億ドル(約2,370億円)、2026年には56億ドル(約8,280億円)の負債を返済する必要があり、これは1996年以来の最高水準だという。





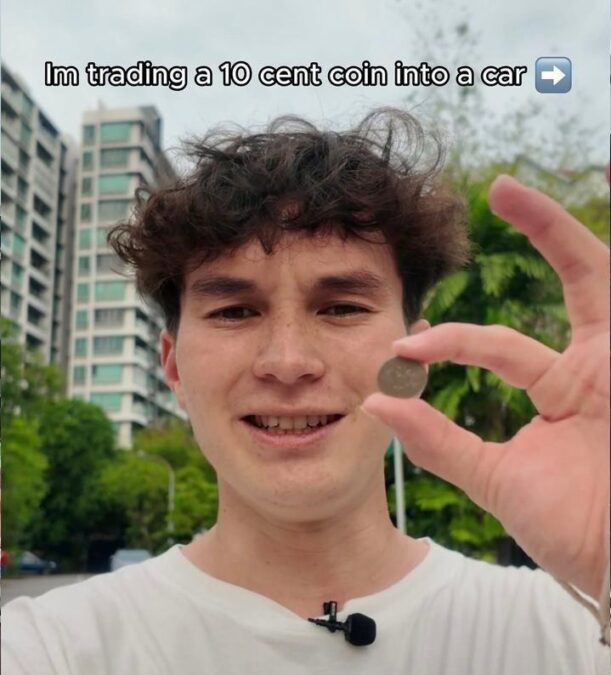















コメント0