米国の宇宙産業を代表する商業宇宙飛行連盟(CSF)は、中国が今後5~10年のうちに米国を追い抜き、世界最大の宇宙大国になる可能性があるとする報告書を発表したと、米科学メディア「ライブサイエンス」をはじめとする海外メディアが伝えた。
この報告書は、わずか2週間前に米上院商業委員会の公聴会で、中国が有人月探査競争で米国を上回る可能性が議論された直後に発表された。公聴会では、ジム・ブライデンスタイン前米航空宇宙局(NASA)長官が「NASAの予算削減が撤回されない限り、米国が中国の計画に追いつく可能性はほとんどない」と警告していた。

「レッドシフト」と題された今回の報告書は全112ページにわたり、中国の新たな宇宙ステーション、衛星コンステレーション、有人月探査や月面基地建設など幅広い宇宙計画に関する最新情報をまとめている。
報告書は「中国は単なる追随ではなく、スピードを主導し、規制を緩和し、時に地球と宇宙におけるリーダーシップの再定義に挑んでいる」と指摘した。そのうえで「厳格な政策、戦略的投資、飛躍的な技術発展を背景に、中国の宇宙能力の拡大は世界的な権力競争の構図を根本的に変えている」と分析した。
最大の懸念として報告書が挙げるのは、中国が1972年以来初めて人類を月に送り込む国となる可能性だ。NASAのアルテミス計画はスペースXの大型ロケット「スターシップ」の開発遅延で停滞しているが、中国は2030年の有人月着陸を目標に主要な節目を次々と達成している。これには月面の精密マッピング、月のサンプルの地球へ持ち帰り、独自の超大型ロケット開発などが含まれる。NASAは2027年までに宇宙飛行士の月面着陸させることを目指している。

さらに中国は、2035年までに自律型原子炉を備えた完全稼働の月面基地建設を計画している。これは希少な月資源の確保を主張する手段となり、将来の火星探査競争で優位に立つ足掛かりになるとの見方もある。
低軌道分野でも競争は激化している。中国は最近「天宮」宇宙ステーションを完成させたが、国際宇宙ステーション(ISS)が退役すれば唯一の国営ステーションとなる。NASAは民間企業と連携して次世代ステーションの開発を進めている。一方で中国は、スペースXの「スターリンク」に対抗する独自の衛星ネットワーク構築にも取り組んでいる。
報告書は、中国の急成長を可能にした要因として、商業宇宙企業への巨額投資や、ロシア、インド、日本を含む各国との協力姿勢を挙げている。
この報告書の共同執筆者で米アリゾナ州立大学の宇宙政策アナリスト、ジョナサン・ロール氏は「中国の宇宙能力の進展の速さには驚かされる。大学院時代にはこの分野を十分理解していると思っていたが、わずか3年後にはほとんどの知識を更新せざるを得なかった」と語った。
一方で米国の宇宙産業は、トランプ政権下でNASA予算がほぼ半減された影響で大きな制約を受けている。
CSFのデイブ・カボサ会長は「米国はいまだ多くの分野で優位にあるが、中国は非常に速いペースで前進している。積極的に対応しなければ、5~10年以内に追い抜かれる可能性がある」と警鐘を鳴らした。

















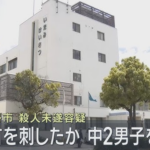




コメント0