日本が輸出可能な防衛装備は現在5種類に限定
救難・輸送・警戒などの制限撤廃を検討
年内に与党協議会設置、来年の国会での実現を目指す

日本政府と与党が、輸出可能な武器を5つの類型に限定している現行の運用指針を撤廃する方向で本格的な議論に入った。制限が撤廃されれば、日本の殺傷能力を持つ武器の輸出が大幅に拡大する可能性がある。
朝日新聞が12日、複数の関係者の話を引用し、自民党と日本維新の会は年内に与党協議会を設置し、来年の定期国会で「5類型の撤廃」を実現する方針を固めたと報じた。
この「5類型」は、2014年に従来の「武器輸出三原則」に代わって制定された「防衛装備移転三原則」の運用指針に基づくもので、日本が輸出できる武器を「救難・輸送・警戒・監視・掃海(機雷除去)」の5種類に限定している。
この規定の下で日本が完成品の武器を輸出した例は、フィリピンへの警戒監視レーダー輸出の1件にとどまる。自民党内では、こうした制限が「防衛産業の成長を阻害する足かせ」として、かねて見直しを求める声が強かった。
しかし、これまで連立与党を組んでいた公明党が慎重姿勢を崩さなかったため、議論は停滞していた。ところが、先月の自民党総裁選後に自公連立が解消され、保守色の強い日本維新の会が新たな与党パートナーとして加わったことで、5類型撤廃論が一気に現実味を帯びてきた。
実際、自民党と維新の会による連立合意文書には、「2026年の通常国会で5類型の撤廃を実現する」と明記されている。
朝日新聞によれば、高市早苗首相の政権発足後、国家安全保障局(NSS)や防衛省などではすでに5類型撤廃に向けた内部検討が始まっている。運用指針から関連文言を削除し、完成品の武器輸出を幅広く認める方向が有力視されている。
また「防衛装備移転三原則」で定める輸出目的を「国際平和への貢献・国際協力の推進に資する場合」や輸出先を「同盟国など」といった制限も見直し、対象国と目的の大幅な拡大を検討しているという。
なお「防衛装備移転三原則」およびその運用指針の改定はいずれも法改正を伴わず、政府・与党内の手続きのみで実施可能とされる。

高市首相は今月5日の衆院本会議で「自民党と日本維新の会が5類型の撤廃で合意した」と述べた上で「防衛装備移転三原則の運用指針見直しを早期に実現できるよう、具体的な検討を進める」と表明した。
また、小泉進次郎防衛相も11日、防衛装備庁主催のイベントに寄せたビデオメッセージで「運用指針の改定を早期に実現するため、関係省庁と連携して検討を進める」と語った。
日本は1967年に「武器輸出三原則」を定め、共産圏諸国や紛争地域などへの武器輸出を原則として禁止してきた。
その後、野田佳彦政権下で一部例外が認められるようになり、第2次安倍晋三政権の2014年には「防衛装備移転三原則」が制定され、同盟国との共同開発や技術移転が可能となった。
一方、「強い日本再建」を掲げる高市政権は、防衛力強化政策を加速させている。政府は近く発表する総合経済対策の三本柱の一つに「防衛力・外交力の強化」を掲げ、5類型撤廃による防衛産業の活性化をその中核に据える方針である。
また、政権発足直後から「安全保障関連3文書の早期改定」や防衛費増額の検討を進めており、国家安全保障戦略の再構築に着手している。







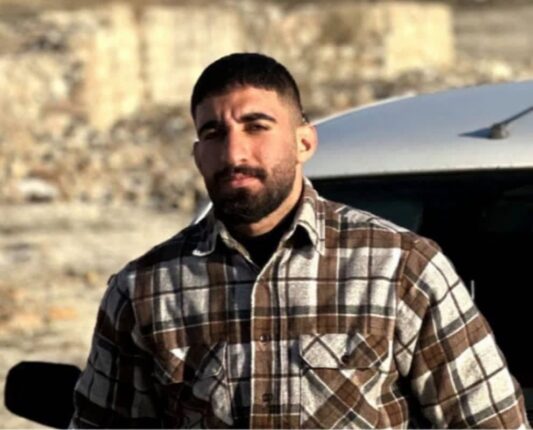













コメント0