日本の造船業復活、官民で1兆円を投入へ…独占禁止法も緩和
造船再生ロードマップ…1兆円を投入
2035年までに年間建造量を2倍に
基金創設で設備投資・人材育成を後押し
国内造船会社の統合も原則許可へ

政府が造船業の再建に向け、官民協力で総額1兆円を投じる。経済安全保障の観点から海上輸送能力を確保するとともに、研究開発を強力に後押しするため、専用の基金を新設し、数年にわたり安定的に資金を供給する方針だ。
14日付の読売新聞によると、政府は近く策定する総合経済対策にこうした内容を盛り込んだ「造船再生ロードマップ」を盛り込む見通しだ。
ロードマップでは、2035年までに現在の年間建造量(約910万総トン)を2倍に引き上げる目標としている。2035年までに政府と造船業界がそれぞれ約3,500億円を出資し、残りは財政投融資を活用する公的金融機関が拠出する案が検討されている。
新設される基金は、事業者による継続的な設備投資を支援するために活用される。
官民資金は造船関連の人材育成にも充てられる。AIやロボットなど先端技術を活用した造船技術のほか、水素やアンモニアといった新燃料で航行する次世代船の開発支援も行う方針だ。
造船業の競争力強化に向けて、国内造船会社の統合も原則として認める方向で調整が進んでいる。読売新聞によると、公正取引委員会は近く経済産業省の専門家会議で、造船業を念頭に「寡占状態にある国内企業同士が統合・合併しても、海外に有力な競合企業が存在し、競争への影響が大きくないと評価できる場合は独占禁止法上問題にならない」との見解を示す予定だという。
これまで企業側は、合併規制違反や談合など独占禁止法違反の懸念から統合・合併に慎重だった。公正取引委員会の意見表明は、国際競争力確保のため大型投資が必要になる中で、統合のハードルを下げて企業の投資を促す狙いがあるとみられる。
日本の造船業は1990年代初頭には世界の建造量の約5割を占めていたが、2023年には約2割まで低下した。事業撤退が相次ぐ中で危機感が高まり、国際物流の大半を海上輸送に依存する日本にとって、造船業の再建は切迫した課題となっている。
また、米国との協力強化の観点からも造船業再生は重要視されている。造船業は、日米の関税協議において日本が投資を約束した重要産業の一つであり、国内の造船環境を整えることは、米国の造船業復興に寄与するための事前作業でもある。日本経済新聞は、日本のこうした政策について「日米が本格的な協力に入る前に、日本がまず国内の基盤を固めようとする動きだ」と分析している。
政府は先月28日の日米首脳会談で、造船所の近代化に向けた戦略的投資を行うことで米国と合意し、覚書を交わしている。




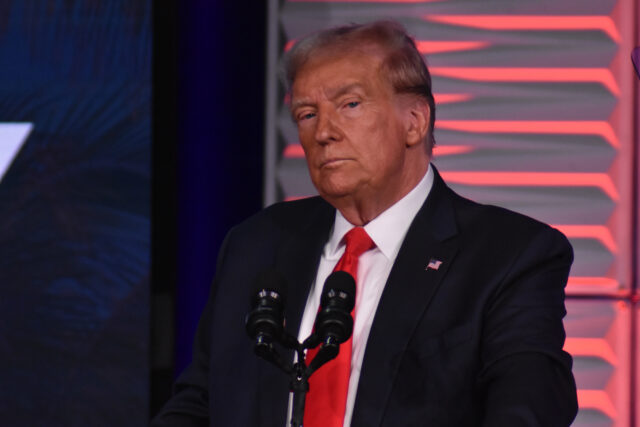





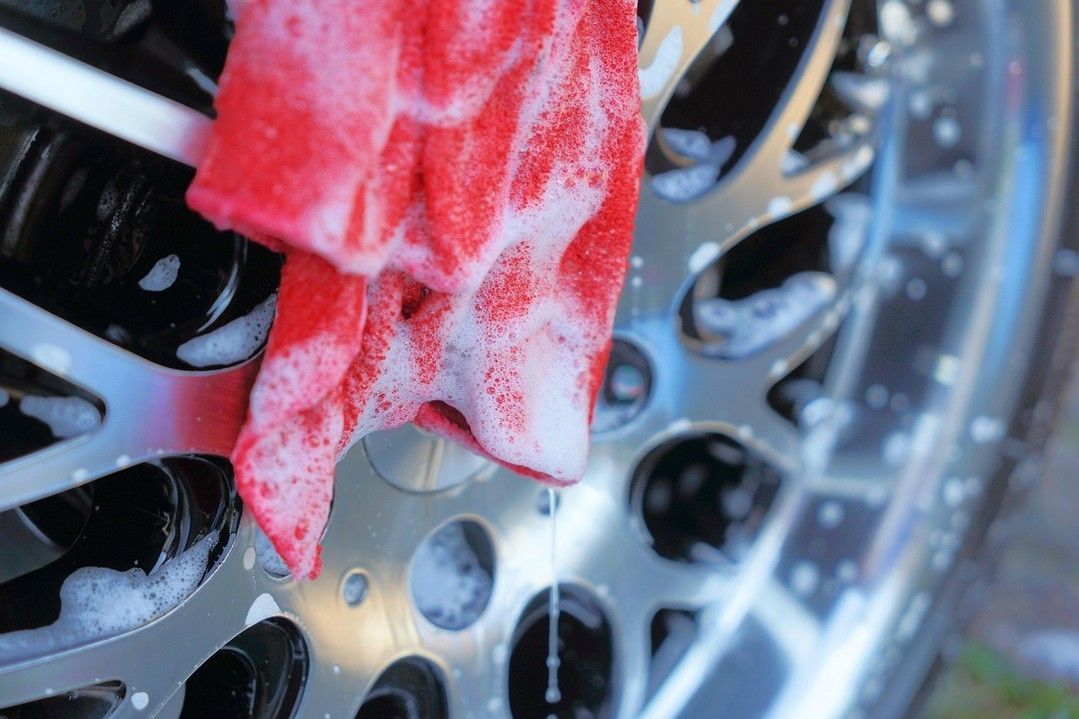


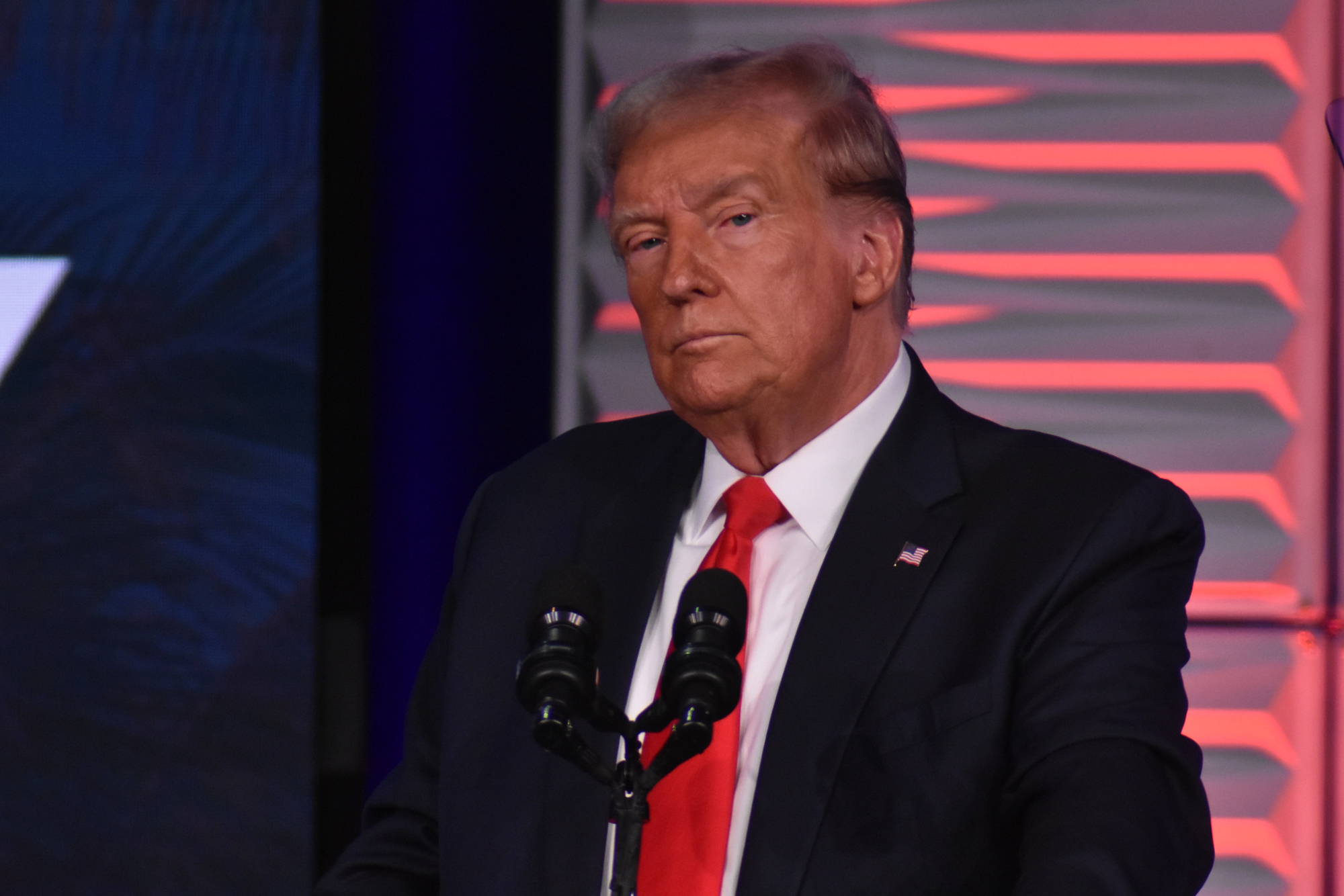







コメント0