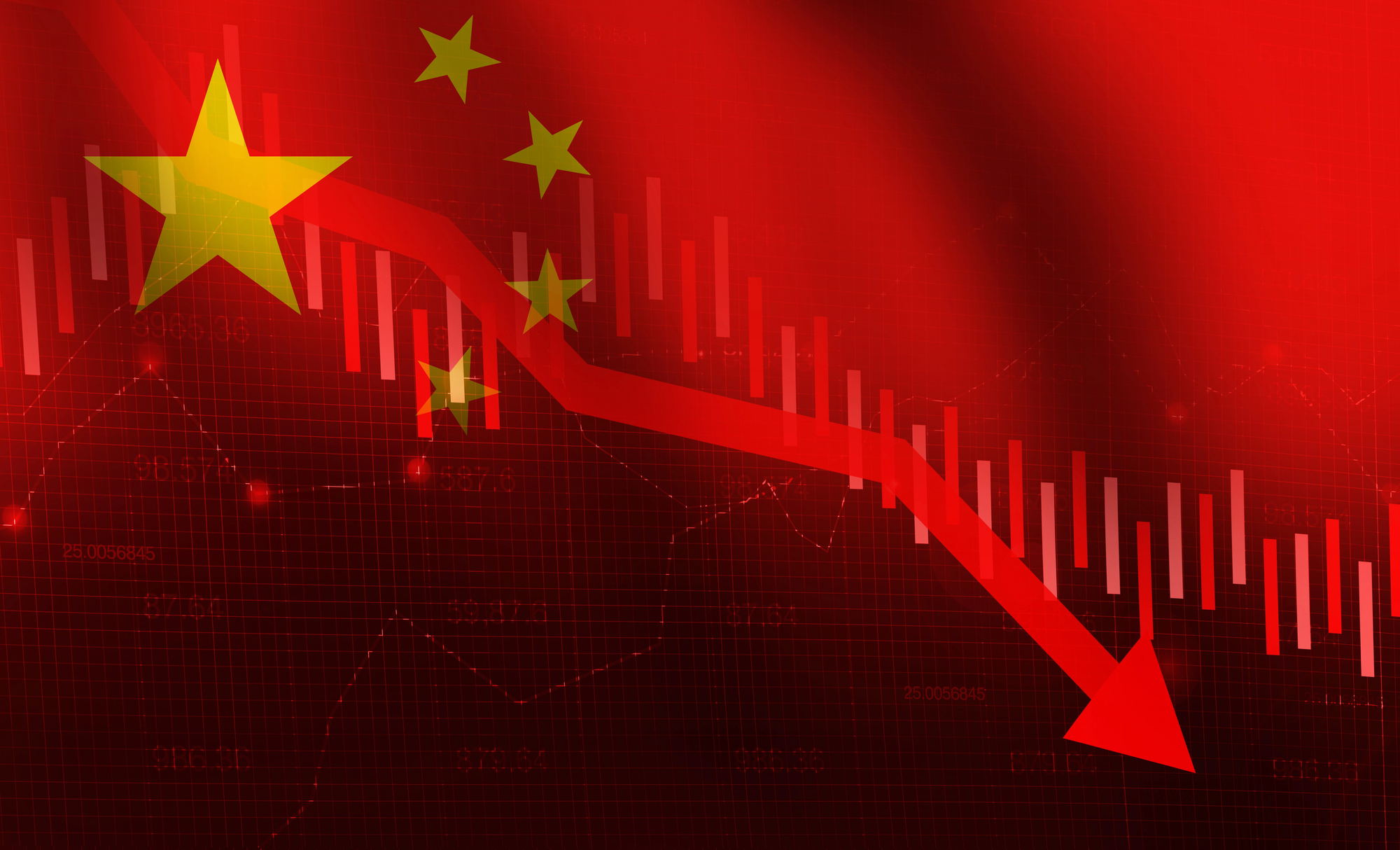
中国の10年物国債金利が史上初めて日本の国債金利を下回った。中国経済は低成長局面に陥る一方、日本は「失われた30年」という長い暗黒のトンネルから抜け出し、景気回復の兆しを見せているとの見方が出ている。
25日、日本経済新聞(日経)によると、中国の10年物国債金利は21日に年1.83%台になり、日本の10年物国債金利(年1.84%台)を下回ったという。統計作成を開始した2000年9月以降、両国の10年物金利が逆転したのは今回が初めてだ。10年物国債金利は国債市場の基準だ。これまで30年物と20年物国債金利は日本が中国より高くなっていたが、逆転現象が10年物国債にまで広がった。
中国の10年物国債金利は、ここ2か月以上底値付近で横ばいしていた。経済成長率が鈍化するなど主要経済指標が期待を下回り、投資家が相対的に安全な国債に資金をシフトしたためだ。一方、日本では政府の大規模な財政拡大がインフレ圧力を高め、国家債務の負担を増す可能性があるとの懸念が広がり、国債金利は2008年以来の最高水準まで上昇した。両国間の金利差は過去最小水準まで縮小し、史上初の金利逆転につながった。
中国と日本の10年物国債金利の逆転は、正反対の方向に向かう両国の経済状況を鮮明に示すものだとの解釈が出ている。中国は内需不振の中、デフレ危機から依然として脱却できていない。10月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比で2.1%下落し、37か月連続の下落傾向が続いている。
一方、日本は消費者物価指数(CPI)の上昇率が3%前後で推移し、インフレ状況が欧米を上回る水準だ。これにより、中国は不動産市場の低迷と内需不振、輸出鈍化が重なり、かつての日本と似た長期低迷局面に入りつつある。対照的に日本は不動産バブル崩壊後「失われた30年」と呼ばれる長期デフレーション(景気後退の中での物価下落)からの脱却を試みている。
ブルームバーグは「投資家は、今の中国は日本がかつて経験した長期低迷の役割を引き継ぐ一方で、日本は数十年に及ぶデフレから脱却しつつあるという構造的変化を価格に反映している」と説明した。






















コメント0