「肥満・血糖異常予防にオクラが効果的」
野菜のオクラが幼児期の過剰栄養による肥満と血糖異常の予防に効果があるという研究結果が発表された。

最近、国際学術誌「サイエンスダイレクト」に掲載された論文で、ブラジルのマトグロッソ連邦大学の研究チームは「生後間もない時期の過剰栄養で代謝障害が発生したラット(実験用のネズミ)にオクラを食事補助として与えた結果、エネルギー代謝と血糖バランスの改善効果が見られた」と報告した。
研究チームは、生後3日のラットの母乳摂取量を調整するため、1匹の母ラットに対する子ラットの数を3匹(少数グループ)と8匹(通常グループ)に設定した。さらに、少数グループを2つに分け、通常の飼料(SD)とオクラ1.5%添加した飼料(AE)を与え、生後60日までの代謝変化を追跡した。
実験の結果、少数グループの母ラットの母乳は中性脂肪とエネルギー含量がより高く、このグループの子ラットは通常グループと比べてより多くの母乳を摂取した。しかし、オクラを添加した飼料を与えたグループは、通常の飼料グループに比べて肥満と代謝異常が顕著に減少し、特に脳視床下部の炎症性サイトカイン値が有意に低下した。炎症性サイトカイン値が高いと慢性炎症を引き起こし、肥満や糖尿病の原因となる。
研究チームは、この結果がオクラの抗炎症作用と抗酸化作用によるものだと説明した。特に視床下部の炎症改善とインスリン感受性の回復が主要なメカニズムだと分析した。オクラに豊富に含まれるポリフェノール、カテキン、ケルセチンなどの生理活性物質が代謝症候群の予防に寄与するという。
研究チームは「今回の研究は、生後間もない時期の過剰栄養が将来の代謝疾患の主要因となる可能性があり、オクラのような機能性食品による非薬物的介入が予防策となり得ることを示唆している」と述べた。
オクラは熱帯・亜熱帯地域で主に栽培される緑色の細長い莢状の野菜で、独特のぬめりと食感、香ばしい味が特徴だ。オクラは日本の食文化に欠かせない食材で、茹でて和え物にしたり、冷や汁、サラダ、丼物、天ぷらなどさまざまな料理に使用される。
















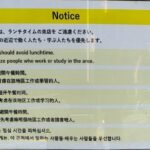





コメント0