
夜ごと寝返りを繰り返し、眠れぬ夜を過ごす人が増えている。
スマートフォンの使用、不規則な生活リズム、ストレスなど、さまざまな要因が不眠症の一因となる中、「メラトニンサプリメント」に注目する人もいる。中でも、日光を浴びることで体内で生成されるという特性に着目し、メラトニンが睡眠とどう関係するのか、また実際にサプリとして効果があるのかを知りたいという関心が高まっている。だが、ここには一般的によくありがちな誤解がある。
よく混同されがちな「メラニン」は、皮膚や髪、目の色を決める色素成分で、紫外線から体を守るために日光を浴びることで生成が促される。一方、「メラトニン」は脳の松果体から分泌されるホルモンで、主に睡眠と密接に関係している。日中に十分な日光を浴びると、夜に自然とメラトニンの分泌が増え、体に「眠る時間だ」と伝えるのだ。
メラトニンは「睡眠と覚醒のリズム」を調整する、体内時計の役割を担っている。日が暮れて暗くなると徐々に分泌量が増え、眠気を促す。逆に朝に日光を浴びると、分泌が抑制され、すっきりした目覚めをもたらしてくれる。
しかし、睡眠障害や時差ぼけ、深夜勤務などによってメラトニンの分泌リズムが乱れると、眠りづらさを感じるようになる。こうしたケースでは、メラトニンサプリメントが一時的に体内時計を整えるのに役立つとされている。実際、米国食品医薬品局(FDA)もメラトニンを睡眠補助目的での短期使用に限り、安全性を認めている。
ここで強調すべきは、メラトニンが「睡眠薬」ではないという点だ。睡眠を強制的に誘導するのではなく、「今は寝るべき時間だ」と脳にサインを送る、いわば体内時計のリセット役に近い。そのため、サプリメントを摂取する際は、部屋を暗くし、スマートフォンなどの強い光を避けるなど、就寝環境を整えることが重要となる。

メラトニンは比較的安全とされるが、長期間かつ高用量で服用すると副作用が生じる可能性がある。代表的な症状として、朝のぼんやり感、頭痛、めまい、体内時計の乱れなどが挙げられる。特に、妊婦や授乳中の女性、うつ病の既往歴がある人は、必ず医師に相談した上で服用すべきである。また、睡眠薬や血圧薬、抗凝固薬などとの併用により薬物相互作用が起こる可能性があるため、注意が必要だ。
さらに、子供への投与は成長ホルモンとの関連が指摘されるため、自己判断での服用は避けるべきだ。つまり、メラトニンは短期服用が原則で、長期間にわたり不眠に悩んでいる場合は、メラトニンを摂るよりもむしろ睡眠習慣の改善を優先すべきである。
自然なメラトニン分泌を促すためには、メラトニンサプリメントに頼らずとも、朝に十分な日光を浴びることが重要である。朝に光を浴びると、脳は「今は昼間である」と信号を受け取り、メラトニン分泌を抑制する。これに対して、夜になると分泌が増加する。毎日決まった時間に起床し、日光を浴びる習慣をつけることで、体内時計が安定し、メラトニンの自然な分泌が促進される。
結局のところ、メラトニンサプリメントはあくまで補助手段に過ぎない。健康的な睡眠は、規則正しい生活、適切な睡眠環境、そしてストレス管理といった総合的な習慣から生まれるものだ。


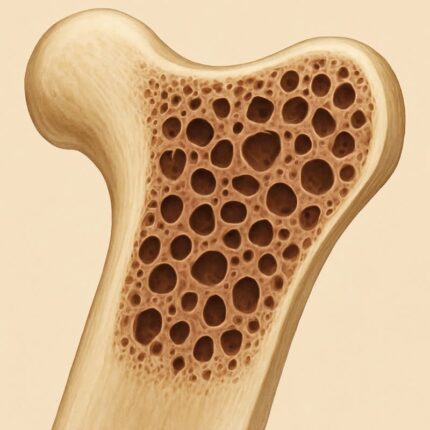
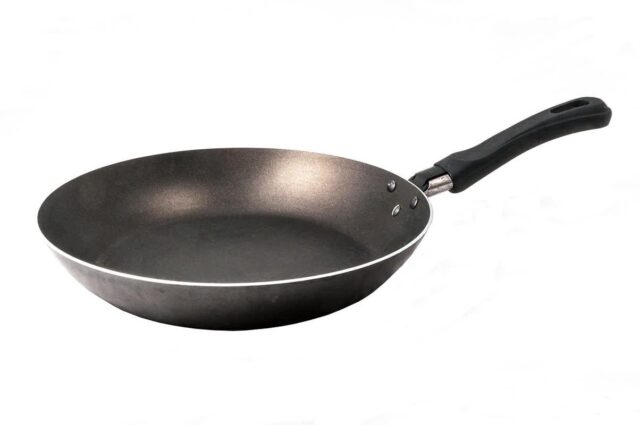








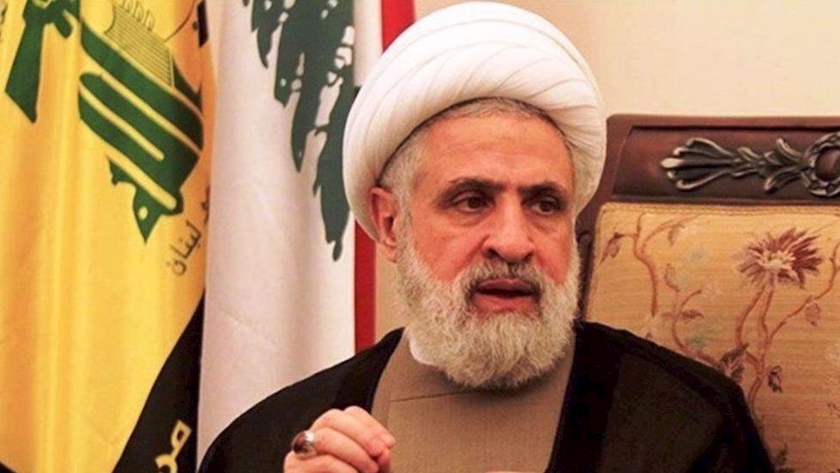


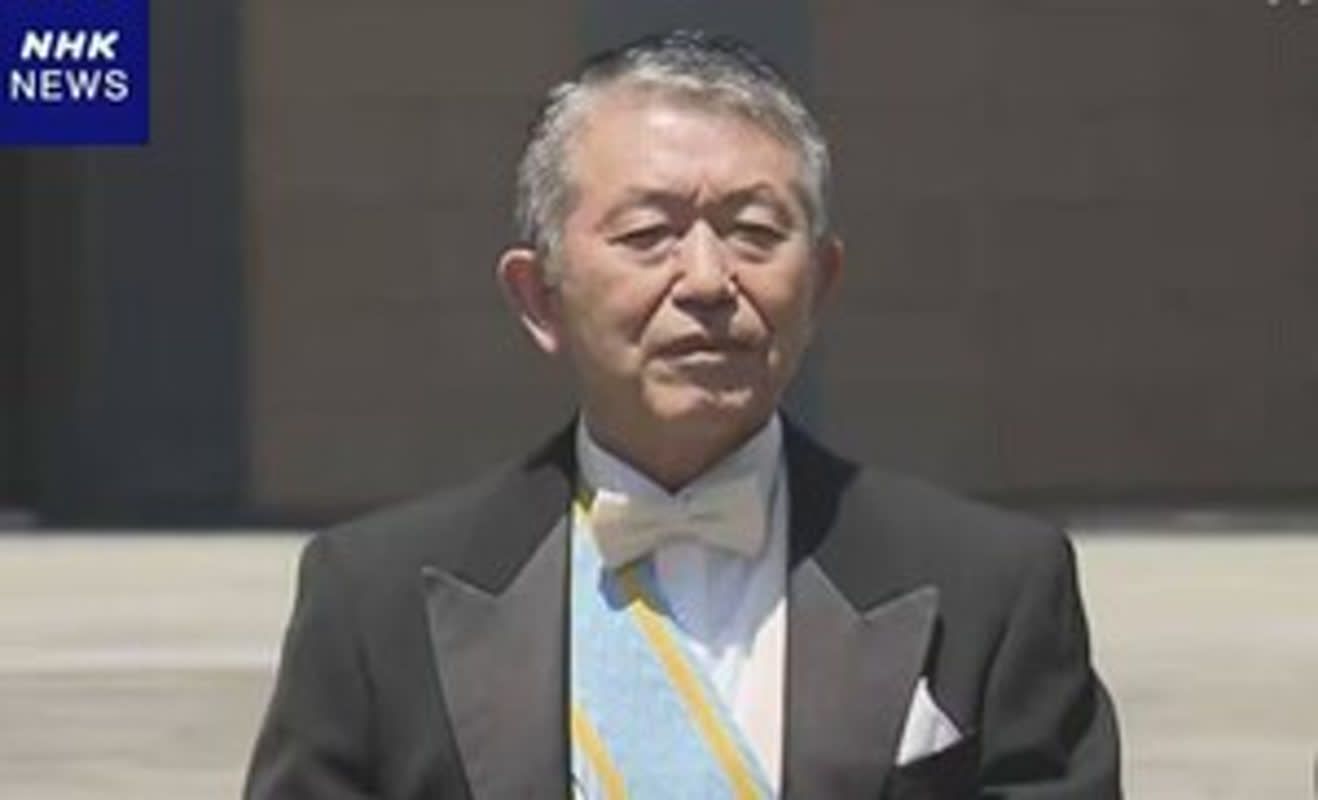






コメント0