
中国の電気自動車(EV)生産能力は供給過剰だが、国内需要が不足している。そのため、価格引き下げと輸出に注力し、世界市場で「EVデフレ」を引き起こしているとの分析が出た。
「ニューシス」の報道によると、米国のテスラは米国内の主力モデルの最低価格を10%引き下げ、日産自動車の日本国内主力EVは来年、前モデルより価格が下がる見込みだ。これらが代表的な例として挙げられた。
「日経アジア」は14日、テスラが7日に米国などでフラッグシップモデル2台の価格を引き下げたと報じ、「EVデフレ」の広がりを分析した。
テスラのモデルYの基本価格は、従来より5,000ドル(約75万2,103円)安い39,990ドル(約601万5,704円)となった。ただし、バッテリー容量の減少に伴い走行距離も10%短くなった。
米国は先月末、7,500ドル(約112万8,226円)だったEV税額控除を終了し、モデルYを含むベストセラーモデルの価格が実質20%上昇した。テスラは顧客流出を防ぐため、即座に低価格モデルを投入しました。
テスラのイーロン・マスクCEOは以前、3万ドル(約451万2,873円)未満の低価格車を発売する計画を明らかにしていた。
日経アジアは、米中貿易戦争がコスト削減を制限する可能性があると指摘した。
テスラはバッテリーとモーターに必要な希土類のほとんどを中国から輸入している。中国は米国との関税交渉で優位に立つため、希土類の生産・輸出管理を強化している。
この生産・輸出管理によりコストが上昇する可能性がある。
GMとフォードもEV価格を段階的に引き下げる計画だと日経は伝えた。両社とも3万ドル未満の新型EVを発売する予定だ。
先進国の中でEV普及率が比較的低い日本でも価格引き下げが進んでいる。
日産自動車は8日、フラッグシップEVリーフの全面改良型基本モデルの推奨小売価格を、従来モデルより6万円安い約519万円に設定したと発表した。
日本の自動車メーカーの価格引き下げ圧力は、世界最大のEVメーカーである中国BYDの影響を受けている。
BYDは日本市場進出のため価格攻勢に出て、今年9月に日本で人気のEVの価格を50万円引き下げ、117万円に設定した。
世界のEV価格下落は、自動車バッテリー市場での中国メーカーの優位性とも関連している。
世界シェア1位の中国バッテリー大手CATLは、欧州自動車大手ステランティスとバッテリー工場に共同投資し、価格引き下げによる攻撃的なマーケティングを展開する予定だ。
EVの核心部品であるバッテリーの価格引き下げは、必然的にEVの「デフレ」につながる。
グローバルコンサルティング会社アリックスパートナーズによると、今年7月時点で中国のEVメーカー(ハイブリッド含む)は129社に上る。
中国では習近平国家主席が直接、過当競争による出血を禁じるほど、まさに無差別な価格競争が繰り広げられている。
国内市場の需要が限られているため、輸出量を増やしながら中国だけでなく世界中に価格引き下げの連鎖が広がる可能性がある。
このような中国企業の攻勢は自動車に限らず、EVも他の品目に劣らず激しいとの見方がある。
日経の「EVデフレ」は、こうした中国製EVの氾濫がもたらす現象を指していると分析されている。










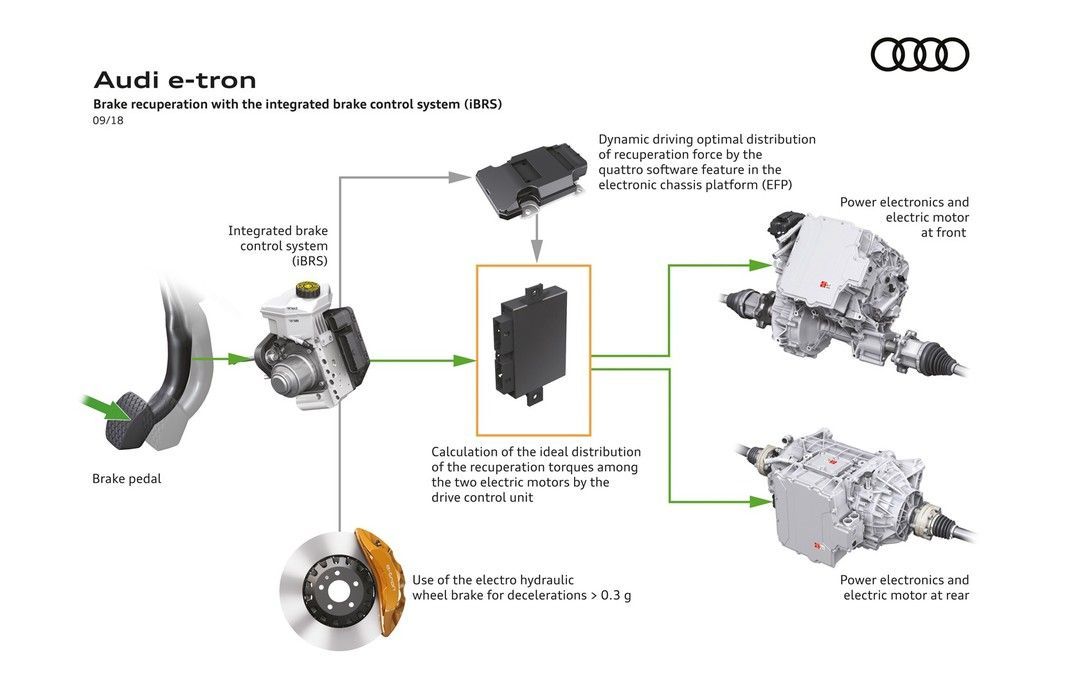











コメント0