
健康のために果物を摂る人は多い。だが、全ての果物が無条件に抗がん効果をもたらすわけではない。
むしろ、特定の果物は摂取方法を誤ると、がん細胞の成長に必要な栄養素を供給する「餌」となり得る事実を知っているだろうか。
医師は、抗がん効果を期待して果物を無分別に摂る習慣が逆効果になる可能性があると警告している。
甘味の強い果物、糖分が問題

ブドウ、マンゴー、バナナなど糖度の高い果物は、ブドウ糖の含有量が多い。ブドウ糖はがん細胞が最も好むエネルギー源で、過剰摂取はがん細胞の増殖を促進する恐れがある。
実際、血糖値を急激に上昇させる食品を多く摂る人ほど、一部のがん発生リスクが高いという研究結果が報告されている。
誤解しやすい「抗酸化果物」

ブルーベリー、ザクロ、オレンジなどの抗酸化果物も、闇雲に多く摂ればよいというわけではない。抗酸化成分は細胞の損傷を防ぎ、がん予防に役立つが、糖分の過剰摂取はその効果を相殺してしまう。
問題は、抗がん効果だけを信じ、1日に果物を過剰に摂る習慣だ。適量を超えると、抗酸化効果よりも血糖値上昇が大きな問題となる可能性がある。
果物摂取時に守るべき原則

果物は1日1〜2回、1回に握りこぶし大程度が適量である。可能ならGI(血糖指数)が低いリンゴ、梨、ベリー類を選ぶのが望ましい。果物ジュースより丸ごと食べる方が血糖値の上昇を抑えられる。
また、がん治療中の患者は必ず医療スタッフと相談し、摂取量を調整することが安全である。
がん予防に本当に役立つ食習慣

抗がん効果を最大限に引き出すには、果物だけでなく、野菜、穀物、タンパク質をバランス良く摂取することが重要だ。特に野菜に豊富な食物繊維は、血糖値を安定させ、腸内環境を改善し、がん予防に好影響を与える。
「果物=抗がん剤」という単純な見方は危険な誤解だ。糖分の多い果物は、逆にがん細胞の餌になる可能性があるため、適切な量と種類を選ぶ必要がある。
今日からは果物を闇雲に多く摂るのではなく、適切な量と方法を守る賢明さが求められる。これこそが真のがん予防につながる賢明な食習慣だ。




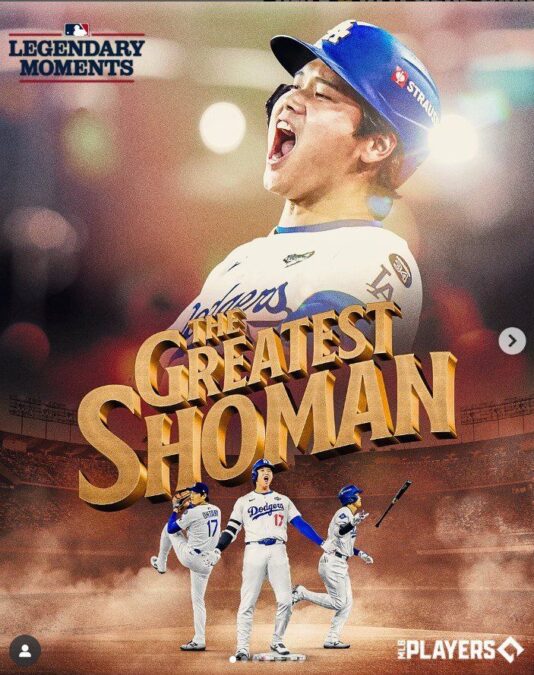
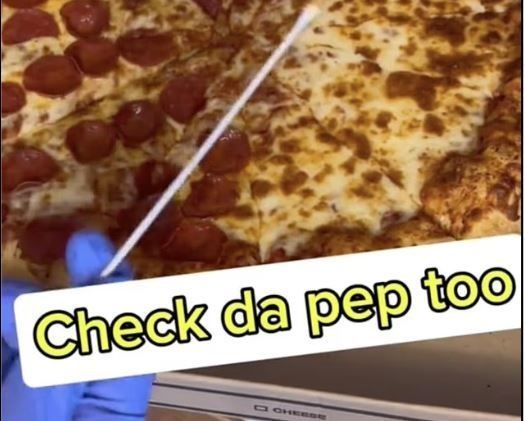

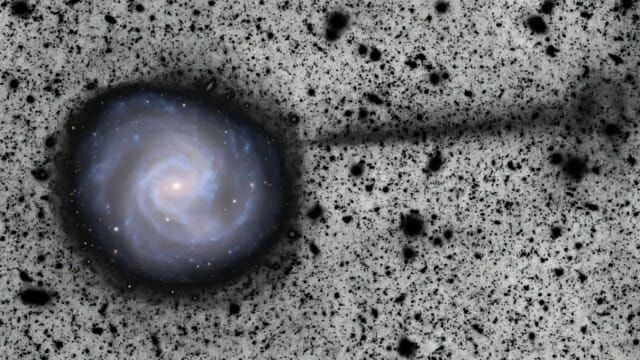














コメント0